国際経済の基礎テキストを読んでいたら、比較優位の理論の話が出てきた。
超ざっくり言えば、「国によって生産が得意なものと、苦手なものがあるが、得意なものだけを生産し、苦手なものはそれを得意とする国から輸入した方が効率が良い」ということだ。
例えば、日本は工業品の生産が得意だけど農業品の生産は苦手、米国は工業品の生産が苦手だけど農業品の生産は得意だとする。この場合、日本は工業品の生産に特化して農業品は輸入し、米国は農業品の生産に特化して工業品を輸入すると、両国を合わせた生産が最大化する。
この比較優位の考え方を示すため、経済学のテキストでは、アインシュタインと弟子(あるいは秘書)のたとえ話がよく採り上げられるという。
アインシュタインという大学者が大きな研究テーマに取り組んでおり、研究には創造的な作業と、文献の調査や計算といった補助的な作業が必要だとする。
アインシュタインには1人の弟子がいて、この弟子はどちらの作業についてもアインシュタインより能力が劣るとする。弟子は創造的作業についてはアインシュタインの4倍の時間がかかり、補助的作業については2倍の時間がかかるとする。
この場合、アインシュタインは弟子に任せず、全て自分でやった方が早いような気がするが、実際はそうではない。
1日は24時間しかないので、弟子に補助的な作業を任せ、自分は創造的な作業に専念した方が遙かに生産性を上げられるのだ。実際に数字を使って検証すると次のようになる。
アインシュタインが創造的作業1単位にかかる時間が2、補助的作業1単位にかかる時間が2とする。
弟子が創造的作業1単位にかかる時間が8、補助的作業1単位にかかる時間が4とする。
このとき、アインシュタインが創造的作業に使う時間を6増やすと、創造的作業の達成量は3増える(6÷2)。一方、補助的作業に使う時間はその分(6)減ってしまうので、その達成量も3減る(6÷2)。
補助的作業が3減ったので、それを弟子が補うため補助的作業に当てる時間を12増やす(4×3)。このとき弟子の創造的作業の時間は12減るので、その達成量は1.5減る(12÷8)。
二人の作業を合計すると、総労働時間は(配分を変えただけなので)同じだが、創造的作業の達成量は1.5増え(3-1.5)、補助的作業は変わらない(-3+3)。
頭がこんがらがるかな?
つまり、2つの仕事のどちらでもアインシュタインに劣る弟子だが、比較的得意な方の仕事に注力すれば、アインシュタインの作業効率向上に役立つのである。
このモデルを究極的に広げれば、「何をやっても他人に劣る人(すなわちダメっ子)でも、自分の中で得意なことを一生懸命やれば、世の中の役に立つ」と結論づけることができる!
世のダメっ子よ、奮い立て! つまり苦手なことは、もうやらなくていいのだ!
その方が後ろめたい思いはしなくていいし、世のためにもなるぞ!
と、強気なコメントを残したものの、責任は持てないダメっ子であった。
ちなみに読んでいる本はこちら。分かりやすいし、幅広いテーマを扱っている良書だと思う。


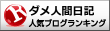




コメント