ダメっ子は、自分のダメさを棚に上げて、世間の言葉の使い方に異議を唱えたくなることがときどきある。細かいところが気になってしまうのが、ダメっ子の悪い癖…。
さて、近年、「競合」という言葉が「競争相手」の意味で使われるのをよく見聞きするが、これってどうなのよ? 例えば、次のようにいう。
日本の自動車メーカーはGMの競合だ。
十数年前から、だんだんよく見かけるようになってきた。特に経営学関連の文脈で頻繁に目にする。以前は比較的専門性の高い文章で見ることが多かったが、最近は一般的な文章でも見かける。
この言葉の使い方に僕が違和感を感じるのは、次の理由からだ。
僕の認識では、「競合」という日本語は、競い合う関係にある「状態」を表す言葉である。したがって「競合する」とか「競合を避ける」といった使い方をする。
現に、手元にある国語辞典をひくと、次のように定義されている。
- きそいあうこと。せりあうこと。「環境保護と開発とが—する」
『広辞苑 第六版』 岩波書店 - ① いくつかの事柄が同一の対象のうえに重なり合うこと。また、せりあうこと。
② 私法上、単一の事実または要件について、評価あるいはその効果が重複すること。また、刑法で、一個の行為が数個の罪名にあたること。
『精選版 日本語国語大辞典』 小学館 - 〖名・自サ変〗
➊〖他サ変〗互いにきそいあうこと。「大手企業が―する国際市場」「―商品」
➋いくつかの要素が重なり合っていること。「―脱線」
『明鏡国語辞典』 大修館書店
この定義に基づくと、「A社とB社は競合している」とは言えるが、「A社はB社の競合である」とは言えない。
では、なぜ「競合」が競争相手(特に「競合企業」や「競合商品」)の意味で使われるようになったのだろうか。
原因は英語の翻訳にあるような気がする。「競合」の訳語として、まず思いつく英単語は”competition”である。周知のとおり、「競争する」という意味の動詞”compete”の名詞形だ。
このcompetitionには「競争という行為」「競合する状態」の他に、まさに「競争相手」の意味もある。
今度は英和辞典を参照すると、次のように定義されている。
n.
1 競争,争い,張り合い;(商売敵などから仕向けられる)競い合い,仕掛け戦:
2 (賞品・名誉・利益を得ようとする)試合,競技会,コンペ:
3 ⦅通例 the competition⦆ 競争相手;⦅集合的⦆ 競争者:
『ランダムハウス英和大辞典(第2版)』 小学館
つまり、Japanese automakers are GM’s competition. という言い方を普通にする。
あくまでも推測だが、経営学の英語文献の翻訳で、こうした文脈の”competition”の訳語に「競合」が使われたのが発端で、冒頭の使われ方が広がったのではないだろうか。おそらく、最初にその訳語を使った人は、日本語の「競合」の意味を正確に知らなかったので、英和辞典に書いてあった訳語をそのまま使ってしまったのだろう。
上述のように、僕の感覚では、この「競合」の使い方は非標準的だ。おそらく一定年齢以上の新聞記者も、僕と同じように感じていると思われる。だから新聞では、この用法はあまり見かけない。以前は全然見なかったが、最近は時々見かけるようになってきたので、もしかしたら若い記者が使っているのかもしれない。
言葉は生き物なので、この使い方も今後ますます浸透してきて、正しい用法になってしまうのだろう。だとすれば、新しい時流に乗れず、古い考えに固執してしまうダメっ子がいけないのかもしれないが、どうも納得がいかない。

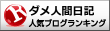

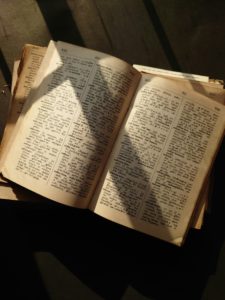


コメント