こんにちは、実務翻訳者のぴぴおです。

翻訳をしていると、翻訳が単純作業に思えて飽きてきてしまうことはありませんか。
実は私も、いつもではないのですが、ときどきそうなることがあります。
翻訳が作業に感じられてしまうと、つまらなくなります。すると長く続けられなくなるので、一日の作業量が落ちます。
作業を効率化するためにツールを使ったりしても、あまり効果はありません。
そして、このような心理状態で作った訳文を後で読むと、大抵、原文の構造に引きずられて硬かったり不自然だったりします。
どうしてこのようなことが起こるのかといえば、翻訳に取り組むときの意識の持ち方が悪いからだと、あるとき気づきました。
逐語訳の問題
ここからは、英語から日本語に翻訳するという前提で話を進めていきましょう。
翻訳というと、英語の単語や表現を日本語の単語や表現に置き換えること、というイメージを持つ人が多いかもしれません。
そのイメージに則って、原文を意味のまとまりごとに区切って、それを日本語に置き換え、つながりが良くなるようにある程度調整を加えるという工程を経ると、日本語の文章らしきものが出来上がります。
しかし、英語と日本語では、基本的な文法構造が大きく異なるだけでなく、コロケーション(特定の形容詞と名詞あるいは名詞と動詞などの単語の結びつき)や、話者が一般的に前提として持っている知識など、異なる要素が数多くあるので、フレーズの置き換えを基本とする「置き換え型」翻訳では訳文の不自然さがなかなか解消できません。
改善策
この問題を克服する効果的な方法は、翻訳に対するアプローチそのものを変えることです。
具体的には、まず原文をしっかり読み込んで、内容をできるだけ深く正確に理解します。そして、その内容をいったん頭にため込み、自分の言葉でその内容を書き直すのです。
つまり、フレーズの置き換えという意識を捨て、読み取った原文の内容を日本語で再表現するという意識で取り組めばよいのです。
そうすると、置き換え型の翻訳に比べて、原文を読み取るのにやや時間がかかるかもしれませんが、多くの場合、訳文はよりスムーズに頭から出てきます。
時々、原文の内容をうまく言い表す日本語がなかなか見つからず、時間がかかることもありますが(そのようなとき、私は日本語の表現力を磨く必要性を改めて認識します)、その他の部分で時間を短縮できているので、こういうところに時間をかけられます。
再表現型の翻訳のメリット
こうして作成した訳文は、原文の構造や表現をあまり意識しないで作られているため、自然な日本語になります。また、自分で文章を書くときのように一気に訳文を吐き出せるので、たいていは処理スピードも上がります。
さらに、このような考え方で翻訳に取り組むと、翻訳が単純作業ではなくなり、よりクリエイティブな活動になるため、飽きずに長時間続けられます。
したがって、こうした「再表現型」のアプローチを取れば、置き換え型の翻訳に比べて速くたくさん訳せて、なおかつ訳文の質が高くなるというメリットがあるのです。まさにいいことずくめです。
単純に速さだけを極めようとすれば、ツールなどを利用してフレーズ置き換えの効率をひたすら上げればよいのかもしれませんが、それではやっていることが機械と大差ありませんし、スピードではどうあがいても機械に勝てません。
機械翻訳が大きく進歩している今こそ、翻訳者は再表現型の翻訳を追求するべきなのでしょう。
スランプに陥ったときは、このことを思い出すようにしています。

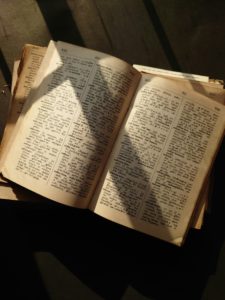


コメント