こんにちは、実務翻訳者のぴぴおです。

英語の総合力を効率的に伸ばす方法としてシャドーイングが知られています。今回はこのシャドーイングについて説明しようと思います。
シャドーイングとは
ご存じの方も多いと思いますが、シャドーイング(shadowing)とは、聞いた言葉を、聞き終わらないうちにそっくりまねて発音していく学習方法です。通訳の初期のトレーニングにも使われているそうです。
このトレーニングで向上が期待できることとしては、(1)発音、(2)リスニング能力、(3)語彙・表現力、(4)スピーキング能力、などが挙げられます。
シャドーイングで学習効果が表れる仕組みや、実際の学習方法については「外国語を話せるようになるしくみ シャドーイングが言語習得を促進するメカニズム 」(門田修平 著)という本に詳しく書いてあります。以下では、この本の内容をダイジェストで紹介します。
シャドーイングを通じて上記のような成果が得られるのは、以下の4つの効果が働くからだそうです。
- インプット効果:聞こえてきた英語の音声を捉えようとし続ける結果、英語のリスニング能力が向上すること。
- プラクティス効果:耳や目を経て知覚した単語・表現・構文を声に出して繰り返す結果、声に出さずに心の中でリハーサルする力が鍛えられ、単語・表現・構文が意識的に検索しなくてもすぐに取り出せる知識として身につくこと。
- アウトプット効果:スピーキングのプロセス(状況を把握する、発言すべき内容を考える、表現・構文を探す、発話する、など)の一部をシミュレーションする結果、スピーキング能力が向上すること。
- モニタリング効果:自身の学習経験で得た知識等に基づき、自身の言語能力の実態を把握し(メタ認知)、さらに今後の学習法を調整すること。
上記の1~3は順に発現すると予想され、4はこれら全てを支えるような仕組みになっているそうです。
したがって、シャドーイングで効果を出すには継続的に実行する必要があると言えます。
どれだけやればいいのか
どれくらいやると、どのような効果があるのでしょうか。本書では、以下のような発達が想定されています。
- 1万語:復唱能力の発達
- 3万語:発音の高速化
- 10万語:リスニング能力の向上(インプット効果)
- 30万語:語彙・構文の内在化(プラクティス効果)
- 100万語:スピーキング能力の自動化(アウトプット効果)
シャドーイングの練習をすると、次第にインプット音声を正しく復唱する能力がまず発達します。すると、この復唱能力に引っ張られる形で発音速度が高速化します。この2つの能力がアップすると、音声の知覚能力が上がり、リスニング能力が上がる(リーディング能力との差がなくなる)というのが10万語までの流れです。
ここまで来ると、その後の飛躍的な能力の向上が期待できます。30万語に向かうと、語彙や増え、定型表現や構文が自然に頭に入るようになります。そしてその知識の脳内検索を繰り返し実行することで、徐々に自動化した英語の運用能力が身につきます。
30万語を超えて100万語に向かうと、これまでのプラクティス効果で無意識に獲得した語彙・定型表現・構文を実際のコミュニケーションで意識せずに自動的に活用できるようになります。ここまで来ればペラペラと言えるのではないでしょうか。
ちなみに、実施語数はどの時点でカウントするのか(例えば、1回実行したら数えるのか、当該テキストのシャドーイングを完全にマスターしたら数えるのか)という疑問が生じるかもしれませんが、本書に具体的な記述はなく、あくまでも目安だということでした。要は、コツコツ続けていると次第に上記の効果が出てくるので、たくさんやり続けましょうということだと思います。
具体的な方法
さて、そんな効果が期待できるシャドーイングですが、具体的にはどのように練習したらよいのでしょうか。本書に書かれていた手順と幾つかの注意点を挙げます。
シャドーイングは以下のステップを踏むと効果的なようです。
- リスニング:普通に聞く。一度だけでOK。一度聞いてほぼ概要がつかめる素材を選ぶ。
- マンブリング:マンブル(mumble)とは、ブツブツつぶやくこと。本格的シャドーイングのリハーサル。いきなりシャドーイングは難しい場合に小声でやってみる。これでシャドーイングが可能な素材かどうかを判断する。これも一度でOK。
- パラレル・リーディング:テキストを目で追いながら行うシャドーイング。リスニングやマンブリングで聞き取れなかった箇所を中心にテキストを参照する。必要がなければスキップしてよい。(a)テキストの音読に重点を置いて、必要に応じて音声に注意を切り替える、または(b)音声を聞いて復唱しながら、聞き取れない部分があったらテキストに注意を切り替える、のどちらかを意識的に実行するとよい。
- 意味チェック:分からない単語や構文があれば、辞書などで調べる。
- プロソディ・シャドーイング:プロソディ(prosody)とは韻律のこと。英語の発音に注意を向け、できるだけそのまま模倣する。自分なりの発音に変えて復唱しないこと。苦もなくできるようになるまで練習する。
- コンテンツ・シャドーイング:文の意味内容を楽しみながら、同時に口からスラスラと復唱した音声が出てくる状態になるのが目標。単語の意味や構文を瞬時に頭の中から検索する訓練になる。これができればシャドーイングは完成。
- リピーティング:この先はテキストが特に気に入った場合や、時間に余裕がある場合に行う発展トレーニング。文単位で音声を止めてポーズを置き、いったん記憶して、それを繰り返す。上記6までが完全にできた状態から始めるのが大事(不正確な発音が定着する恐れがある)。英文を覚えるための学習法という趣旨を理解して行うと、語彙や構文の定着が促進される。
- レシテーション:テキスト全体を苦もなく言えるまで暗唱する。プレゼンの練習にもなる。
上記の手順で練習を行うにあたり、幾つか注意点があります。本書で挙げられていたものを以下に抜粋します。
- 適切な素材を選ぶ:テキストのわかりやすさ、音声の速さなどが自分のレベルに合っていることが大事。「読んでほぼ完全に分かる」よりも一、二段階優しいテキストが良い。また、内容に興味があるものを選んだ方が続けやすい。
- できる限りインプット音声に集中する:単語や構造が分からなくても、インプット音声そのものを楽しみながら復唱に集中し、リズムやイントネーションもしっかりまねるようにする。練習を続けて楽に復唱できるようになると、余裕ができて自然に意味も頭に入ってくる。
- 定型表現に注目する:the thing is that…、that reminds me of…、whatever it is…など、定型表現に注目してそれを習得すると、リスニングにもスピーキングにも役立つ。
- うまくできずに間違えたり、飛ばしたりしても、気にせず立て直して継続する:ストレスをためずに気楽にやる。
- メタ認知能力を養う:自分のシャドーイング状況をモニタリングして、うまく実行しているかどうかをチェックして、必要に応じてやり方を是正する力を身につける。この能力は語学の力を伸ばすのに大事だと、本書の著者は強調しています。
お勧め教材
シャドーイングの教材として、著者は以下のものを推奨しています(本書より一部抜粋)。
全般:初級~上級まで
入門・初級
・[CD付]決定版 英語シャドーイング<入門編>【改訂新版】
中級
上級
・英語シャドーイング―映画スター編〈Vol.2〉【CD2枚付き】
ぴぴおのお勧め
「英検1級 文で覚える単熟語」
他の級も同じシリーズがあるので、自分のレベルに合わせて選べます。単語・熟語、リーディング、リスニングが学べる良い本だと思います。
ペラペラを目指して、100万語のシャドーイングにチャレンジしてみましょう!



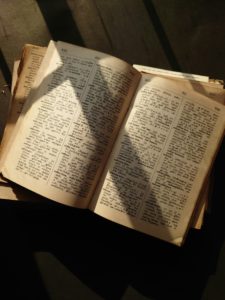


コメント