こんにちは、ダメっ子のぴぴおです。
翻訳者の間では近年、人工知能(AI)が脅威になっています。
数年前にGoogle翻訳の精度が上がって以来、機械翻訳で生成される訳文が「内容が分かり、自然に読める水準」に達することが多くなってきたからでしょう。
しかもテキストをコピペして翻訳ボタンをクリックすれば、結構まとまった量の訳文が一瞬にしてできあがります。このスピードは人間には太刀打ちできません。
これでは「もう翻訳者なんていらないよ」と思う人も多いでしょう。
僕はおよそ10年前に、20年後には機械翻訳が翻訳者の脅威になっているかもしれないとブログに書いていましたが、そうした時代は予想より早く近づいているようです。
しかし、Google翻訳などの機械翻訳による訳文と原文をよく比べて読むと、意外に穴があることが分かります。原文にあって訳文にない要素(あるいはその逆)があったり、自然な日本語にはなっているものの、原文と内容が違ったりすることがあるのです(まったく逆の内容のことすらあります!)。
これではビジネスや出版などの正式な翻訳には使えません(使って大変な目に遭った企業や団体などが幾つかありましたね)。
機械翻訳で作った訳文を後で人間が修正すればいい(いわゆるポスト・エディット=PE)という意見もありますが、実際にやってみるとあまり省力化にならないうえ、どうしても作られた訳文に引きずられてしまうため、訳文の質も上げにくいという問題があります。
ただし機械翻訳の精度は日々向上しているので、こうした問題も徐々に解消していくかもしれません。
それでも、まっとうな翻訳をしている人は、機械翻訳にはまだまだ負けないでしょう。
なぜなら、機械翻訳は結局のところ、原文のテキストをデータとして処理しているだけで、原文の内容を「理解」しているわけではないからです。
そのため、テキストの背景にある情報、ソース言語(原文)の読者とターゲット言語(訳文)の読者が前提として持つ知識の違い、前後の文章の流れ、原文の筆者が強調したいことなどを踏まえて、適切な訳文を作るということができません。
学校英語的に構文を分析して、辞書に載っている訳語を当てはめただけの訳文は、機械翻訳に早晩追い抜かれるでしょうが、原文のメッセージを深く正確に理解し、理解したメッセージをターゲットの言語で再表現するというプロセスで作成された訳文は、機械翻訳では不可能な、非常に付加価値の高いものになると思います。
そうした訳文が作れれば、機械翻訳にまだまだ勝てるはずですし、翻訳者として十分な報酬を得ることができるでしょう(ただしそのためには、こうした訳文の価値を理解してくれるクライアントを見つける必要がありますが)。
いずれにしても、これから翻訳者として生き残るには、AIができない付加価値の高い訳文を作れるようになることが必須条件でしょう。
僕もこの辺を意識して、また翻訳の勉強や仕事に力を入れ直そうと思います。



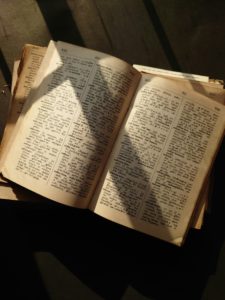


コメント